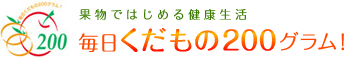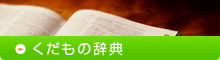|
うめの野生種の分布は日本、朝鮮半島、台湾、中国南部に限られ、他の果実に比べると比較的狭い地域に限定されています。日本でも古くから栽培されていましたが、その目的は花の鑑賞用で果実は利用されていませんでした。果実が利用されるようになったのは、鎌倉時代以降とされていますが、そのころの品種は中国から伝えられたものか、日本の野生種から育成されたものかは不明です。果実の利用が盛んになったのは江戸時代に入ってからといわれ、京都の内田梅の系統が全国に伝えられ、それぞれの地域に合った品種が育成されました。 |
|---|
 |

日本の主要生産県は、次のとおりです。うめは全国で栽培されていますが、うめの形質の強い小玉系は西南暖地に限られています。また、うめの品種には地域特産的品種も多く、東日本の白加賀、群馬の養老・花香実、和歌山の南高・古城、徳島の鶯宿・林州等がその例としてあげられます。 |
|---|
 |
うめの品種は、1果実重が10グラム以下の小玉系、10〜30グラムの中玉系、30グラム以上の大玉系に分けられます。うめとあんずは遺伝的に極めて近縁関係にあり交配も可能であることから、中・大玉系品種にはあんずの形質がかなり入っていると考えられています。 出荷は小玉、中玉、大玉の順になりますが、品種や熟度により加工適性が異なり、梅酒やカリカリ漬けには小玉や中玉品種の新鮮な青うめが、梅干しにはある程度熟度が進行し、青味がやや薄らいだ中玉や大玉品種が適しています。一般に青果として小売店で販売されているうめは、梅酒用として収穫されています。 主な品種は以下のとおりです。
|
|---|
 |
生(青)うめの主要出荷時期は6月ですが、小梅の早いものは5月下旬から出荷されています。生うめは主に梅酒用として収穫され出荷されていますが、カリカリ漬け、ジャム、砂糖漬け、煮うめ等にも適しています。梅干しにするには、ある程度熟度が進み青味がやや薄れた果実が適しているので、梅干し用として出荷されているものか、産地からあらかじめ適期に収穫されたものを送ってもらうようにします。 |
|---|
 |
|
|---|
 |
店舗等で販売されているうめは梅酒用のものですが、梅干しやカリカリ漬けにしてもおいしくいただけます。
梅干しの作り方 梅干しには塩漬けしたものを日干ししただけのものと、赤しその葉により紅色に色づけしたものがあります。 原料のうめは、ある程度熟度が進み青味がやや薄れた果実を一晩水に漬けてアク抜きし、水切り後に塩をまぶして漬け込みます。塩の量はうめの量の20%程度とし、うめと塩を交互に重ねますが、塩は上の方をやや多めにします。うめの量の10%程度の重しをし、漬け込むと2日位で漬液が上部に上がってきます。2日経っても漬液が上がってこない場合は天地返しをするか、濃い塩水を少量まんべんなくふりかけます。 日干しは土用のころ(7月上旬〜8月上旬)に日当たりの良いところに果実だけ広げて干し、夕方には漬液に戻すといった作業を3日程度繰り返します。赤しそにより色付けする場合は、葉を塩揉みし、固く絞った葉だけを最初の日干しのときに漬液に入れるときれいに色づくとともに、風味も増します。これを1ヵ月程度、うめが乾燥しない容器に入れて保存すれば、梅干しの完成です。 カリカリ漬けの作り方 原料のうめは青く硬いものを用います。一晩水に漬けてアク抜きをし、水切り後に塩をまぶして容器に入れ、20%の塩水にうめ重量の0.1〜1.2%の焼ミョウバンを加えた溶液を容器の半分程度注ぎ、漬け込みます。塩の量は原料うめ重量の25%程度にします。漬け込み後10日ごろに漬液を捨て、新たに20%の塩水で漬け代えれば長期保存ができます。色づけする場合は、塩水で漬け代えた後に、塩揉みし固く絞った赤しその葉を入れます。
梅酒の作り方 原料のうめは青く硬いものを用います。一晩水に漬けてアク抜きをし、よく水切りします。容器にうめと砂糖を交互にいれますが、最上部には砂糖を多くし、35%の焼酎を静かに注ぎます。砂糖の量は原料うめ重量の7〜10割、焼酎の量は原料うめ重量の5割増を目安とします。砂糖の代わりに氷砂糖を使うと、溶解するまでの時間うめが浮き上がるのを防いでくれます。また焼酎の代わりにウイスキ−やブランデーを使うこともできます。これを密閉して約2ヵ月間、冷暗所で保存すれば飲めるようになります。 |
|---|
 |

うめは、傷みやすいので、買ってきたらすぐに加工しましょう。 |
|---|
 |
うめの一年間の主な栽培管理作業を紹介します。
|
|---|